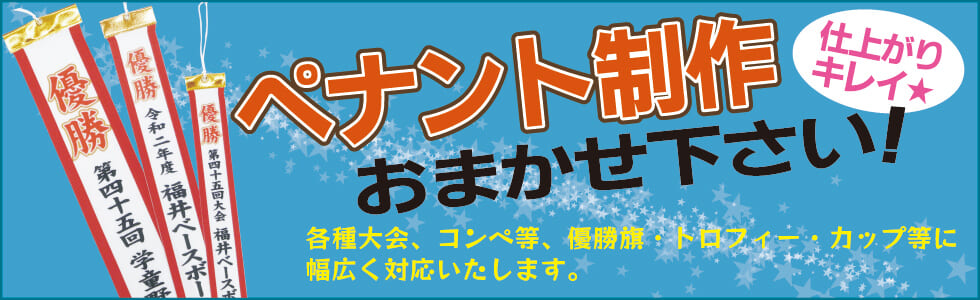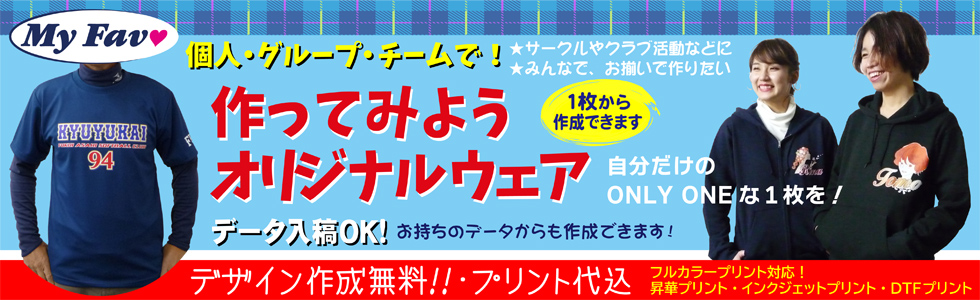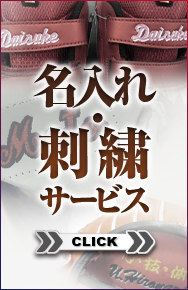野球のボールには、大きく分けて硬式用と軟式用の物があります。硬式用とはコルクやゴムなどの素材にウールを巻き、2枚の牛革をそこに包み、赤い糸で縫い合わせた硬さの硬いボールのことです。軟式用についてはゴムなどの素材で作られていて、中が空洞になっていることが特徴です。
硬式用は主に、高校野球や大学野球、社会人野球、プロ野球に使用され、また最近ではボーイズリーグ、リトルシニアリーグ、ヤングリーグなど、小・中学生の硬式野球チームも増えており使用されています。
軟式用は硬さの柔らかいボールになります。野球のボールに関しては、直径、重量、反発の違いによりA号、B号、C号の3種類に分けられていて、一般用や少年用といったように野球の大会などでは使われる物が定められています。ボールにも歴史があり、サイズの規定などが様々に変化を遂げてきました。現在の軟式用については、大きさや重さ、反発力はこれまでの物と同じですが、飛距離のアップが上昇し、従来のものと比べて変化球が投げやすくなりました。過去にはボールの全面にあったでこぼこ(ディンプル加工)がほとんどなくなることにより滑らかな球体となったことと、縫い目を模した模様を入れたことが大きな変化となっています。でこぼこ感がなくなり滑らかになってしまったために縫い目の模様の存在がボールを握る際に大変に重要となりました。これらの大きな変化により、直球はより伸びるようになり、変化球はより大きく変化するように投げやすくなったのです。反発力は今までの物と同じですが、2バウンド以降の高さを抑えるように設計が成されていることが特徴となります。
軟式ボールのA号、B号、C号の種類は一般の野球の試合などではA号が使われています。B号が中学生用で、小学生はC号を使っています。このように正式な試合などを行う場ではボールが定められているということがあるため、練習を行うときや、練習試合などの正式ではない試合を行うときにでも、普段から定められたボールに慣れておくことが大切なことでしょう。
子供が野球を始めた場合には、最初に基本になる正しいフォームなどを練習によってしっかりと身に付けることが肝心になります。打撃の練習には素振りを行いますが、毎日行うことで正確なバッティングフォームやスイングを身に付けることができます。素振りをするためには練習用のバットを用意すると良いでしょう。毎日素振りを行う際、子供の場合は特に楽しく練習を行うように配慮しないと続けることができないという理由から、試合用のバットは使用せずに練習用の物を用意して使うことをおすすめします。試合用のバットを選ぶ際には体に合った適切な長さや重さの物を選ぶことが肝心になります。長さは、腕の付け根から指先までの長さを測り、その長さに1・3を掛けた数字が体に合った適切な長さの目安となります。重さは、バットを握り先端を軽く振ってみた時に、重さで腕や上半身の筋肉が張るようでしたら、それは体に適していないことになります。それよりも少し軽い物を選ぶようにしましょう。練習用のバットでは試合用の物を選ぶ時よりも少し長めで軽いものを選びます。なぜなら、最初から筋力のない子供に試合用の重いバットを持たせて素振りを始めても、うまくスイングができず、練習そのものが楽しくなくなってしまう恐れがあるからです。軽いバットを使うことで、素早いスイングをすることができることによって練習が楽しくなり、自主的に素振りを行うようになる可能性がでてきます。練習用のバットには金属製の物より木製の物が向いています。竹でできた物がありますが、竹は素振りをした際に芯を外すとしびれるという特徴と、ヘッドが重いため、その重みを利用したスイングを繰り返していくことによって正しいフォームを身に付けることができます。また、丈夫で折れづらいということと、金属製の物のようにボールを打った際に響く音がないために、毎日の練習や夜間の練習にも向いています。バットを振る練習を行う際にはバッティンググローブも用意するとバッティングに役立ちます。素手のままで毎日一生懸命に練習を行っていると、手にマメができてしまい練習の効率が低下してしまう恐れがあるということと、手に力が入りやすくなることで手に汗をかき、汗のためにバットがすっぽ抜けてしまうようなことがあるなどといった事故や怪我に繋がる恐れが考えられます。スムーズで安全に練習を行えるように、バッティンググローブを使用することをおすすめします。
野球をする人であれば持っている道具類に刺繍をしたりマジックを使って言葉を書き込むのは一般的となっています。バットやグラブ・帽子などその熱い想いや好きな言葉を入れることで試合や練習のたびにその言葉を胸に刻み込むのです。
グラブの場合には平裏部に刺繍を入れるのが一般的です。オーダーすればやってもらえます。デザイン面のかっこよさだけでなく、芯が硬くなり硬く頑丈なグラブに仕上がります。
高校によっては未成年者に過度のファッション性は必要ないからと刺繍の色やフォントなど細かく制限されているところもあります。しかしながら、そうでなければ、フォントも業者によってさまざまなものがあり、漢字だけでなく数字やローマ字で入れることも可能です。色もさまざまな色から選ぶことができます。
刺繍場所も平裏部だけでなくどこにでも入れることができます。
メーカーによっては一からオーダーでグラブを作ることもできます。表革の種類も手へのなじみ方や感触・見た目の高級感からさまざまなレザーの中から選べます。裏革も同様です。
表革の一部をメッシュ素材にすれば、普通のグラブよりも軽量化されます。メッシュ部分も色を選べばデザイン的にも違ってくるでしょう。ただ、内野手やミットの場合背面メッシュを選択することはできませんし、高校野球公式大会でも禁止されているので注意が必要です。複雑な文字を刺繍するなら裏革部分でないとメッシュ生地にはやりにくいです。
紐革を断面を白いものにするか表面と同じもの(芯通し)にするか、ヘリ革の種類をどうするか、ハミダシの部分を切りハミにするかパイピングハミダシにするかも選べます。
縫い糸のカラーも変えるとアクセントになるでしょう。ウェブのデザインやバックスタイルのデザイン・芯スタイルや芯の手巻き口方向などこだわればすべて人とは違ったものを選ぶことができ、世界に一つだけのマイグラブができあがるのです。
ただ注意しなければならないのは、高校野球においては用具に関してさまざまな使用制限がなされています。それに違反するものを使っていては公式戦に出ることができません。日本高等学校野球連盟のWebサイトを見れば詳しい制限内容について書かれているので、それを確認したうえで選ぶようにしましょう。
また中学硬式野球や軟式野球なども、高校野球に準じて制限がありますのでご注意ください。
野球用品には何かと規制も多いので、大人であっても社会人野球の公式戦に出るのであれば公式のルールを確認するようにしましょう。
オシャレさだけでなく使い勝手の良さも追求して自分なりのグラブを作りましょう。
野球のグラブはポジションごとに多少の形状の違いはありますが、その構造はおおよそ同じものであり、軟式、硬式ともに構造を同一にしています。ですが、値段、目的によって注目すべき部位があり、グラブを購入するうえで、参考にすべき部分となっています。
まず、ボールを捕球する部位は名称をポケットと呼ばれており、グラブによって大きさ、深さ、位置が異なっています。それはポジションによって用途が変わるためであり、捕球からの素早い送球が必須である内野手はポケットが浅いグラブ、高く上がったフライを適切に捕球しなければならない外野手はポケットが深いグラブと、得意とするポジションによってそれらを見極め、選択する必要があります。どのポジションにおいても捕球は絶対に欠かせないものであるため、ポケットの部分がきちんと作られているものを選ぶことが大切なことになります。
そのポケットの上の部位、網になっている部分は名称をウェブとされており、これもポジションによって形状が異なってきます。投手であれば、対戦相手の打者にボールの握りを窺えなくするためにウェブは隙間のないものになっており、内野手は軽々とした動作を実現するために、ウェブはクロスの形をとった軽いものとなっていることが多くあります。また外野手はフライの捕球時に網の隙間からボールを確認しやすくするために網目の細かいネットになっているなど、ポジションごとに変化があり、ポジションに適したグラブが販売されています。ですが特に規定はなく、自分の好みのウェブを選んでも、支障はないと考えられます。
また、ヘリ皮と呼ばれる部位も、一見地味ではありますが、グラブを選択するうえで重要な部分となっています。ヘリ皮とは、グラブを手にはめた際に、手の甲が見える部分を補強している部位のことで、裁断された皮の強度を高めるために縫いつけられた部分となっています。グラブを選択、使い続けるうえで、ヘリ皮の感触は重要なものであり、皮の質が悪い、また皮が硬すぎるなどの場合には手にうまくグラブが馴染みにくく、使いづらくなってしまいます。そのために購入の際には一度実際に手にはめ、皮の感触を確かめることが必要になってきます。また、高校野球の公式大会ではこのヘリ皮は本体と同色でなければ使用することができない、と規定されているため、確認して購入し、使用することが大切になります。また皮が乾燥しやすく、ひびが入りやすい部位でもあるので、日ごろのメンテナンスが必要となってきます。
グラブを使い込むことによってレース紐が切れてしまったり、緩んできてしまうようなことがあります。紐が切れてしまったまま使うことは危険を伴いますし、緩んでくるとボールを捕りづらくなってしまいます。このような場合はメンテナンスのひとつの作業としてレース紐を取りかえなければなりません。レース紐は野球用具ショップなどで買うことができます。その際、どうせ取りかえるのであれば元々の紐とは別の色の物など自分の好みの色の紐を選ぶといいでしょう。ただし、公式な試合では紐の色に規定がある場合がありますので、派手な色は控えるなどといった注意が必要になります。新品のレース紐をそのままの状態でグラブに通してしまうとグラブ自体が硬くなってしまったり、形が変わってしまうことがありますので、まずは紐にオイルなどを塗って柔らかくする作業から始めます。充分に紐が柔らかくなったらグラブに紐を通していきますが、その際、元々の通し方を覚えておく必要があります。カメラで撮影しておいても良いでしょう。古いレース紐を抜いていきますが、一気に抜くことは避けて、抜いてからその部分に紐を通すということを繰り返していきましょう。専用の紐通しがあるのでそれを使うと穴に紐を通すという作業が楽になります。土手の部分は少しきつくする、ウェブや指先部分は逆に緩めにするなどといった、すぐに使用するための工夫や、自分に合った調整を意識しながら作業を進めていくと良いでしょう。覚えていた元々の通し方のように紐を通すことができたら紐を結びます。結び方については、2本の紐の表側が自分の方を向くように手で持ち、片方の紐を重ねるように交差させ、もう1本の紐を重ねた紐で巻き込むように通し、縦に結び目ができるようにします。縦に結んだ紐の上側を表が見えるように倒していきます。倒した紐に下側の紐も表が見えるようにして被せます。被せた紐をそのまま表を見せたままで上側の紐の下を通していきます。通した紐を少し強めに引いてからもう1本の紐を引くと形が作りやすくなります。このとき2本の紐は表側が自分の方に向いています。しっかりと紐を引いて形を整えて完成です。グラブに元々通されていたレース紐の通し方以外にも通し方は何通りも存在します。人気のある野球選手の持つグラブの紐の通し方と同じように通す人もいます。紐を通す作業に慣れてきたら別の紐の通し方を研究してみるのも良いでしょう。